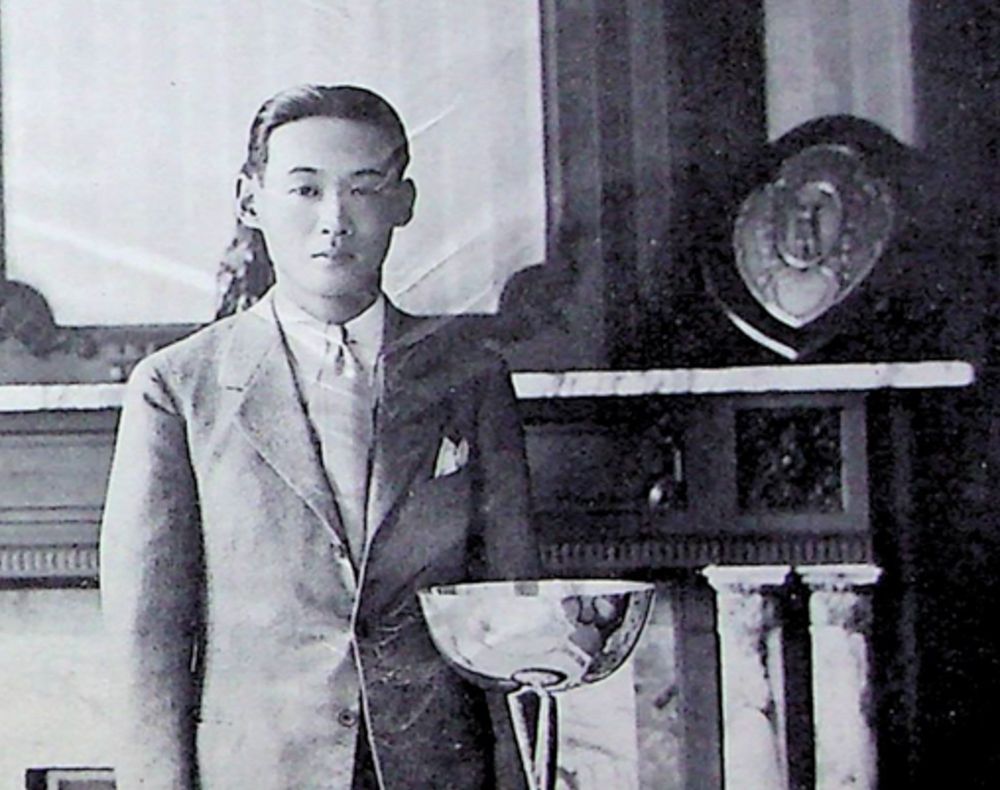HISTORY 組織
日本ゴルフ協会の改組
JGAを揺るがした
戦後の組織改編論争
戦後の日本ゴルフ協会では、全国統一団体としての在り方をめぐって7年にも及ぶ組織改編の論争が展開された。その経緯をたどるには、終戦直後の日本ゴルフ協会の再建から振り返らなければならない。
1942年、戦時下に解散したJGA
日本ゴルフ協会は戦中の1942(昭和17)年10月7日、時の政府からの命令と時局を考慮し、解散する。それまで日本ゴルフ協会が担っていた競技の開催や外国への選手派遣などの事業は、大日本体育協会に代わるスポーツ統括組織として同年4月8日に発足した大日本体育会の打球部会に引き継がれた。
その打球部会は終戦直後の1945(昭和20)年10月5日、部会長である井上匡四郎名で解散が宣言され、終戦処理がなされた。そして、それにともない日本ゴルフ協会の再建が話し合われ、準備委員に井上と前日本ゴルフ協会理事長の石井光次郎が委嘱された。
1949年、日本ゴルフ連盟として復活
1949(昭和24)年、一足早く関西と関東の両ゴルフ連盟が復活。同年、さっそく関西オープン選手権が復活開催された。
その年の11月16日、「正午から、東京・銀座の交詢社に東西のゴルファーが大勢集まり、懸案事項だった全国組織再建のための創立総会が開かれた。これがJGAの、戦後初の会合になった。出席者は旧打球部会役員、関東、関西連盟の11俱楽部の代表だった。ここで『日本ゴルフ連盟』という新連盟の結成(旧日本ゴルフ協会の復興)をみたのである」(『日本ゴルフ協会七十年史』)
この席で理事長には石井光次郎が選ばれ、さらに関東・関西の両ゴルフ連盟から各3名の理事が選出された。関東から選ばれたのは、野村駿吉、藤田欽哉、小寺酉二。関西からは中村寅之助、原田立之祐、乾豊彦が理事に就任する。そして、新しい組織の名称は「日本ゴルフ連盟」としたうえで、連盟の規約は当分の間、旧日本ゴルフ協会の規約を準用。ゴルフルールは原則としてアメリカの新ルールを採用するが、イギリスのスモールボールの使用も差し支えなしとする。競技に関しては、翌1950年から日本ゴルフ連盟主催で日本アマ、日本アマ東西対抗、日本オープン、日本プロ、日本プロ東西対抗などを行うことが決められた。
「こうして始まった戦後のJGA競技は、戦前に比べて大きく転換した。英国のルールを米国のルールに変えることはスムーズに決まったが、協会主催の競技に使用するボールのサイズに関しては問題になった。
関西側はスモールサイズを主張したが、JGAはこれからはアメリカが相手だ、と主張してラージサイズのボールの採用が決定(以下、略)」(『日本ゴルフ協会七十年史』)
翌1950年6月6日、日本ゴルフ連盟はアマチュア東西対抗の競技終了後、第1回総会を開き、名称を戦前の日本ゴルフ協会に変更することを決定する。
「終戦後、日本ゴルフ連盟と称せし理由は、地域的に二分野をなす関東、関西両連盟の協力によって、再組織した結果、結社の上の結社の団体と簡単に思考して採用した名称でしたが、元々この団体は、加盟各俱楽部単位に組織編成せられて居る立場から結社の上に結社がある訳でなく、又社交団体として、時流的いかめしい連盟の名称は芳しからず、従前通り、日本ゴルフ協会(JGA)の通り名をこの際踏襲しては如何と提案せしところ、全代表異議なくこれを賛成した。今後直ちに日本ゴルフ協会と旧称を復活し使用する。
因に、関東、関西の両連盟は従前の如く地域的に日本ゴルフ協会のため、支部としてその連絡事務を代行する」(日本ゴルフ協会 終戦後第一回総会決議録)
JGA改組をめぐる、7年間の論争
1957(昭和32)年、霞ヶ関カンツリー倶楽部で開催され、個人・団体とも日本が制したカナダカップを契機にゴルフの普及に拍車がかかると(一般に「第1次ゴルフブーム」と呼ばれる)、ゴルフ界はより広く「国民のスポーツ」という位置づけへの取り組みが問われるようになった。そのため、日本ゴルフ協会は創立以来の伝統である倶楽部単位の組織を堅持すると主張する関東ゴルフ連盟(KGA)と、地区連盟の連合体で形成すべしとする関西ゴルフ連盟(KGU)との間で、組織として在り方に異論が生じた。そして、その論争はJGA、KGA、KGUの3者間で、およそ7年もの長きにわたって展開されることになる。
「これがJGA史の上で解決までに最も時間を要した『JGA改組問題』である」(日本ゴルフ協会七十年史)
発端は1962(昭和37)年7月6日、JGA会長の石井光次郎宛てに送られてきたKGU理事長・太田垣士郎名の書簡『日本ゴルフ協会改組に関する要望書』にあった。それは、「日本ゴルフ協会の組織は全国統一団体に該当していないから、連盟単位の全国統一機関として改組を要望する」という提言で、そこに至った理由は『KGUの60年史』に次のように書かれてある。
「昭和37年5月24日、KGUの理事会が城陽カントリー俱楽部で開かれた。その折、KGUを中部、近畿、西日本の3地区に分割する案が出された。だが、審議の結果、組織の問題であることから、むしろJGAに改組を要望すべきだとの意見が圧倒的に多く、KGUの分割論を一時棚上げしてもJGAの改組問題を先に解決しようと決議された。
ところが、他にも重要な問題が横たわっていた。加盟費や年会費に関することで、たとえば、一つのゴルフクラブがJGAに加盟しようとすると、まず関東か関西のいずれかの地区連盟に加盟しなければならない。それから先がJGAだが、その時代に地区連盟に加入する場合に20万円の入会金が必要で、さらにJGAにも20万円、そして年会費として地区連盟に10万円、JGAに20万円が必要だった。このため「高い」と不服を唱えるゴルフ場も少なくはなかった。
また、関西地区ではKGUの会員(ゴルフクラブ)になっていたクラブは141。そのうち、JGAに加入していたのが36クラブ。
こうした変則的な面もあり、さらに、なかなか加盟を認めてもらえないというクラブもあったりして、従来の形態を変え、組織の強化を図ろうとする要望だったのだ」
要望の具体的内容は、
- 関東、関西両連盟の連合体として日本ゴルフ協会を形成する
- 地区連盟は自主的運営をする
- 関西地区が二分、三分してもオール関西の競技、事業は合同運営機関を設け処理する
- 日本ゴルフ協会の経費は、地区連盟が一括納入する
- 役員は地区連盟推薦者と、学識経験者で構成する
これを受けてJGAは、KGAとKGUを加えた三者で協議することとして、4カ月後の同年11月、JGA副会長の野村駿吉を委員長とする改組小委員会を開設する。
野村は「JGAを真の意味で全国のゴルフ場とゴルファーの統合機関にしなければ……」と精力的に取り組み、JGAから乾豊彦と小寺酉二、KGAから横田正成、KGUから四角誠一を委員に選出。同年暮れに、
「日本ゴルフ協会を地区連盟単位に改組して東京と大阪に支部を置く。
地区連盟に加盟できる資格は、
- 正会員:在来の会員制のクラブ、ゴルファーの団体
- 準会員:パブリックコース
といった改組骨子案を提示した。
しかし、これにはKGUが反対。JGAの小委員会の内部でも意見が分かれ、合意が得られぬなか、翌1963(昭和38)年に野村が死去(5月13日)。JGA改組は混迷を深めた。
野村のあとは、JGA会長で野村の親友だった石井光次郎が引き継ぐ。委員も一新され、審議の進行役にはJGA常務理事の細川護貞が就いた。
同年8月、細川は「KGA、KGUを解散して各地区の支部協会として発足する。協会に未加盟であったクラブは、自動的に支部協会に入会したものと認め、入会金は不要とする」という私案を作って三者に提示した。しかし、KGAは「JGAの会員はクラブであることを基本線とする」と強硬に反対。JGA改組問題は進展のないまま、時だけが進んでいった。
KGUの『JGA改組に関する要望書』が提案されてから3年経った1965(昭和40)年7月、JGAは停滞する審議の円滑化を図るために特別委員会を発足させる。委員には四つの地区から安田一(関東)、四角誠一(京阪神)、佐々部晩穂(中部)、安川寛(九州)が選ばれ、新たなJGAの組織の大綱を作成する。その中には関西の主張を考慮した規定も盛り込むなどして成立に努めた。
その後も、JGA会長の石井自らが東奔西走。KGA側に説得工作を行ったり、西下してKGUの役員と積極的に懇談するなどした。
ところが、KGAの横田がKGU役員との意見交換会の席上、「個々のクラブがJGAに直結しなければ強化にならない」とKGUとは真っ向から反する組織論を主張。両連盟の歩み寄りは一向に見られなかった。
1971年、各地区連盟が支える
新体制が発足
JGA改組の合意の道が見え始めたのは、1967(昭和42)年のこと。その経緯は『日本ゴルフ協会七十年史』に次のように記されてある。
「改組問題が持ち上がってから5年目の昭和42年(1967)3月、JGAは渡辺実を委員長とする改組委員会を発足させた。岡田信次、佐々部晚穂、細川護貞、山形晋、安田一、加藤武雄、乾豊彦、田中太一、安川寛といった顔ぶれで、翌年2月に改組の規約案、地区連盟案を両連盟に示した。KGUは検討すると表明したのに対し、KGAは「協会の構成は連盟単位案には暫定的に賛成するが、石井会長との約束に基づいて5〜7年の期限をつける」と条件をつけたのだ。
これに対して石井はJGAの理事会において、条件をつけずに改組のスタートを切るよう強力に要請した結果、昭和43(1968)年7月に至ってKGAは、各地区連盟がJGAの下部組織になることを一応了承することを表明したのである。
その骨子はKGUが主張していたように、
- 各地区連盟の連合体によるJGA一本化は関東、関西とも基本線とすることに一致した。
- 地区連盟案の改正点については関東、関西とも概略同様の意見で、条文、会費などについては、今後逐次両連盟の合議の上で改めるべきは改めるとして、一応現状の姿で受け入れる。
- 第一種会員、第二種会員の問題は改組後のJGAで研究し、その具体的な事項もその時点で研究することとし一本化の基本線を進める。
- 関東、関西とも、この問題は連盟の総会に付議決定した後に改めてJGAの総会に付議することとする。
しかし、KGAの役員の中には依然としてJGAから出された案には反対論者が強く、理事長の安田は、①改組は強化にならない、②これ以上の改組は望めない、③次期役員にまかせる(審議の継続)と理事長を辞任する一幕もあった。
1969(昭和44)年2月、JGA会長の石井は長期化している審議に見切りをつけ、KGAの反対意見を押し切るべく、「7月までに改組を行う」と宣言した。その年の7月30日のJGA理事会の席上でKGA常務理事・横田はKGAの意見を出そうとしたが、石井は「JGA総会で公約したものを、いまさら話がつかない、では済まされない」と、改組成立を強く要望した。このため、KGAは、JGA改組委員会で作った会則の改訂案を出すことにした。
同年9月、JGAはKGAから出された改訂案を審議したのを受けてKGUにも図った結果これが了承され、10月13日、岡田、細川、乾、横田の4委員に細目の話し合いをゆだねることにした。同月21日には話し合い事項がJGA理事会で承認され、JGAを解散させ、東西の二つの連盟によって新たに日本ゴルフ協会を創立することが決まったのである。
このように長期化したのは、簡単に片づけられない問題が多かったからだ。JGAは日本体育協会に加盟しているアマチュアの競技団体であることから、全国のゴルフ場を統括するとしても、営利を目的としたパブリックコースを含めるわけにはいかなかった。
一方、KGUには、とかく関東偏重のJGAに吸収されてたまるか、といった面子の問題もからんでいたので、難題の解決には時間がかかった。さらに途中から、どうすれば両連盟に受け入れてもらえるかといった方向に流れたのにも問題があった。
ともあれ、1969(昭和44)年の11月12日にJGAの臨時総会が開催されて組織改革が承認され、26日には新しい理事の決定をみて、1971(昭和46)年1月には新生日本ゴルフ協会が発足し、関東、中部、近畿、中四国、それに九州の各ゴルフ連盟がJGAを支える形になったのである。
文/小関洋
INDEX